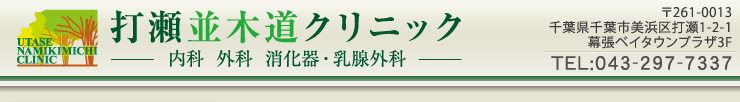口の中のにおいが気になる。よく、こういった患者さんがおられます。
口臭は、他の方とのお付き合いにどうしても気になる、などの問題だけではなく、実は様々な病気の発見の窓口にもなります。
特に、口臭に関係するのは、口腔内と食道・胃といった消化管です。
歯科、消化器・内科の視点から、口臭の原因について、述べてみました。
歯科
口臭の原因には様々なものがありますが、その原因の90%以上はお口の中の細菌が産生する「揮発性ガス」というものです。
この「揮発性ガス」を抑えるためには、「唾液の量」と「お口の衛生状態」が特に需要になりますがその他にも虫歯・歯周病や、食品、全身的な病気なども口臭の原因になりえます。
また、実際には口臭がないのに、本人が気にしすぎるために口臭があると感じてしまう「自臭症」もかなりの割合でみられます。
口臭は唾液の量に気をつけたり、歯磨きをしっかりとおこなうことによってほとんどが予防・改善できますが、虫歯や歯周病などがある場合には先にそれらの治療を行う必要があります。
ですので、口臭治療は実際には、虫歯や歯周病の治療とほぼ同じということになります。
消化器・内科
口につながる内臓として、まず1番に食道から胃・十二指腸があります。
胃は飲み込んだ食物をさらに消化し、その下の小腸へと流すわけですが、胃の流れ、あるいは消化機能が低下し、胃内に食物が停滞すると、口臭を発生します。
代表的な疾患としては、急性・慢性を含む胃炎から始まり、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、また口臭をきっかけとして、胃癌・食道癌が発見されることもあります。
口臭が続く場合には、胃・食道を検査する必要があります。
もう一つの口につながる内臓としては、肺・気管支があります。発熱・喀痰を伴う場合は、呼吸器疾患を考えます。
他にも、糖尿病・肝不全・腎不全が進行した場合には、それぞれ独特の口臭を持つ場合があり、口臭が疾患をみつけるきっかけとなることがあります。
たかやま歯科 TEL: 043-239-7468 http://www.takayama-dc.net/
打瀬並木道クリニック TEL: 043-297-7337 http://namikimichi-clinic.jp |