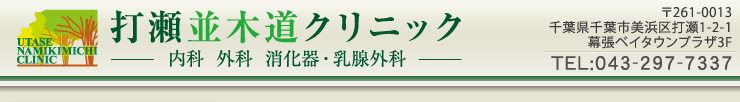厳しい残暑も少しずつ遠のき、涼しい秋風が吹くようになってきました。
今回はインフルエンザの予防について。
一般に言われるインフルエンザは、細菌よりもさらに小さなウイルスが、体内に入り込み、さらに細胞に侵入・増殖することで発症します。
その感染力は強く、毎冬、学校や職場で流行することにより、学級閉鎖などをきたすことで知られます。
予防には、ワクチン接種などが一定の効果を上げていますが、最も大事なことはインフルエンザウイルスの体内への侵入を防ぐことです。
インフルエンザウイルスの感染経路は、感染している患者さんの咳などから、痰とともに空気中に散布されるウイルスが、口や鼻から入り込む、飛沫感染が主となります。
人が密集する満員電車や、教室等で咳をした患者さんの微小な痰が、直接入り込んだり、たとえばつり革等を通じて、まず手に付着し、その手で口の周辺を触ることによって侵入したりします。
また、湿気に弱く、冬には空気の乾燥が流行の原因の一つとなります。
したがって、予防に有効な手段は、古典的なことですが、なによりもまず、ウイルスを洗い流す、手洗いとうがいが大事になります。
外出から帰ったら、まずウイルスが付着している可能性がある外套を脱ぎ着替え、よく手洗いとうがいをすることをお勧めします。
実際に患者さんが集まる医療機関でも、職員がまめに手洗い・うがいをすることで感染を防いでいます。
次に大事なことは、人が集まる場所でのマスクの着用になります。
ウイルス自体は非常に小さいため、マスクの編み目より小さいのですが、実際は空気中に飛沫する痰などに含まれて侵入するので、マスクで痰などの直接の侵入を防ぐだけでも大きな意味を持ちます。
また、人は実は無意識に口の周辺の手を持っていくことが意外に多いのです。マスクの着用はこの手に付着したウイルスのが、口の周囲に運ばれることを防ぎます。
数年前に欧米では、インフルエンザの予防にマスクなどしないから、意味はないとの説が流れたことがあります。
先日、国際的に活躍するインフルエンザの専門家からお話を伺う機会がありました。その際にマスクの効果についても話が及びました。日本では花粉症等でマスクをする機会が多く、街中でマスクをすることに抵抗はないが、欧米ではそもそも街中でマスクをする習慣自体がないだけであり、現在では海外の機関でもマスクのインフルエンザ予防に対する有用性が認められているとのことです。
以前、一日中、口の中を覗いている職業、歯科医の友人に聞いたことがあります。その友人は一緒に働くスタッフも含めて、本当に風邪をひかない、インフルエンザに罹らない。なぜですか?一言、マスクで守っているからさ、の返事でした。
当院では、院内での感染予防を第一に考えています。このため、待合室にはウイルス対応空気清浄器を用いております。
また、インフルエンザワクチンを接種するために来院される方には、一般の患者さんと時間を別にして、専用のワクチン外来を昼の2時から3時の間に設けました。
今後、風邪・インフルエンザの流行期には、院内での感染を防ぐために、職員がマスクを着用いたします。よろしくご理解をいただければと存じます。 |